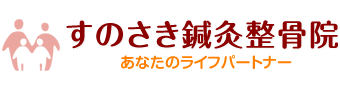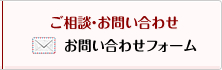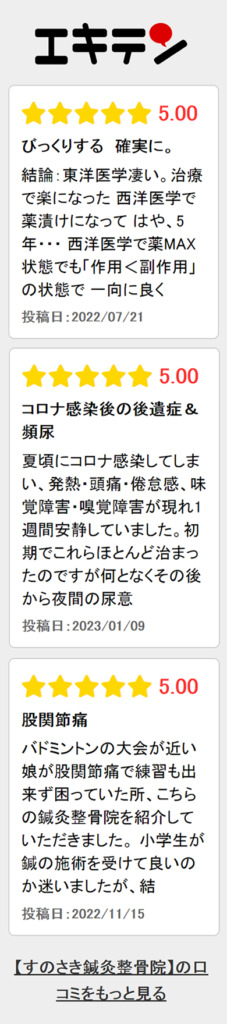痛みや凝り感
痛みや凝り感について
多くの痛みや凝り感は、筋周囲の循環不全(血行不良)により起こります。
原因は様々でありますが循環不全を起こすと温かい血液が届きにくいのでその箇所が冷えてしまいます。
すると、筋肉等の柔軟性が低下して伸びにくくなります。
 |
 |
また、筋肉は弾性繊維を含んでいます。
この繊維は、冷えると硬くなり、温めると柔軟になる性質があります。
筋肉は活動をするのでエネルギーを摂取し排出する“代謝”が盛んに行われます。
しかし、凝り感・痛みあるとこの代謝もうまく行われません。
痛みについて
私達の所へ来られる動機で一番多い症状は痛みであります。擦り傷で感じるちょっとした痛みから、ぎっくり腰のような激痛まで…
ありとあらゆる人生の中で体験した“痛み”は様々であります。
ところで、自分の身体の中で起きたトラブルなのに痛みを伝えるのはとても難しいと思いませんか?
“ズキズキ”・“ピリピリ”・“重だるい”・“刺さるような”など…
痛みの表現方法はあるものの痛みはあくまで主観であり伝えることが難しいものです。
痛みは日常でありふれた感覚であるため、それまでの体験・価値観やその時の状態・精神状態等で判断になり他人と共感するのが難しい感覚でもあります。

患者さんが訴える痛みとそれを理解する私達…
この間に認識のズレがあるとその後の治療効果にも大きな影響があります。そのためカウンセリングを重要視して施術をしています。
背景にある色々な事柄を理解して『なぜ、痛みが起こっているのか?』を共有することで一緒に良い方向へ模索します。
凝りについて、凝りは筋肉の過緊張から
凝りの要因は循環不全であります。
循環不全に陥る原因として“筋肉の過緊張”があります。
筋肉に過緊張があると血液の流れが悪くなります。患部は凝り固まり、圧痛が出現して場合によっては腫れも出現します。
肩や首は、痛みの他に凝りと言う字がよく使われるのには腕や頭の重さの約10~15kgが常にかかっているからです。支えるためにも力が必要であり常に張力を発揮しています。
背中や腰も同様で頭から骨盤(下肢の動きの中心)を人体の後面が常に支えています。
これらは抗重力筋と言って常に重力と向き合うことで身体を支えてくれている筋肉であります。
抗重力筋にかかる力は、姿勢保持目的など小さな力であるため気づきにくいのも事実であります。抗重力筋のように常時、緊張状態にあると血行不良にになりがちです。
私達は二足歩行であるため、仕方がないことを認め目を向ける必要があります。
凝りを揉んではいけない
気持ち良さもあり、自らの手が届く範囲と言うこともあり肩こりがあるとグリグリと揉んでしまうころがあります。
浅い部分にしか手が行き届かないため、返って痛みをぶり返す『揉み返し』を起こしてしまうこともあります。
そもそも、肩こりは筋肉がダメージを受けている状態を示し、そこを揉み叩いたりすることで筋肉を傷つけてしまうこともあります。

この傷を解したときに一瞬肩が軽くなりますが、傷を修復する過程で硬くなるのでさらにダメージを被ることもあるのです。
痛み(凝り)の意味ついて考える
①火災報知器の役割
現在の身体で起きているサインであります。
体のシグナルは安静にして・治療してと言うものです。もしかすると、スケジュールの変更も余儀なくされるかもしれません。ただ、体のこのような働きかけにより無理が出来なくなり、さらに悪化するのを防ぎます。
②慎重さ・警戒心を養う
日常生活での事故を未然に防ぐために“痛い”・“熱い”と言う感覚を養います。慎重に行動したり警戒することでもう二度と同じ目に遭わないように注意することが出来ます。
筋緊張状態をさらに加速させるもの…『姿勢』&『ストレス』
痛いと感じた身体はこの状態から逃れようと、逃避姿勢をとります。
『姿勢が悪くて肩こりになっている』と考える人が多い中、姿勢ではなく肩にアプローチしても意味がありません。

筋緊張は、筋肉の使い過ぎによって起こると考えがちですが“筋肉をうまく使いこなせない状態”でも起こります。
猫背に代表される不良姿勢は脊柱の動きを制限させることで筋緊張を生んでしまいます。姿勢が悪いと抗重力筋に過負荷がかかり本来の筋肉の役割を全うすることができません。
どうしても世の中の風潮としてはその場しのぎが主流になってきています。
原因を解決せず症状だけ取り除くのは、火を消さずに火災報知機を止めることと同じであり、さらに大きな問題を引き起こします。
ストレスからも影響
姿勢と言う言葉の意味には肉体的な姿勢を示す“見た目”があります。また、精神的な姿勢を示す“物事の向き合い方”・“考え方”と言う側面もあります。
企業姿勢、戦う姿勢と言う言葉がわかりやすいと思います。
日常生活における様々な出来事に対する向き合い方=姿勢が悪いとストレス症状に繋がる恐れがあります。
ストレスは生きていく上では避けては通れないものであります。大切なのは、ストレスに対してどのように向き合い、どう対処するかであります。ストレスに対する姿勢は生き様であり、生きる姿勢でもあるのです。
それが肉体的な健康にも影響するので真摯に向き合わないといけません。精神面・肉体面でも多大な影響を与えるストレスは、痛みを考える上で欠かせない要因になってきます。
そして、日本の言葉も奥深いものであります。
『日本の言葉』(新島出著,創元社)にはこう書かれています。
「凝る」は「こころ」と同じ語源である。すなわち「こる」とは凝集していることを指し、 古代人が動物の腹をさいてみると臓腑がいっぱいつまって凝集していることに驚き臓腑のことを「こる」「こごる」といった。
臓腑の中でも最も重要な臓腑は心臓であることから 「こる」「こごる」は臓腑をさす言葉となり、やがて心臓のことを「こころ」というようになった。従って「肩こり」は肩で「こころ」を表しているとも考えられる。
 怒り肩→怒っている様子
怒り肩→怒っている様子
肩を組む→親しく和気あいあいとした様子
肩を持つ→優しく味方をする様子
など、日本語が示す肩こりの様子は奥深いものであります。